 18年後562万世帯が生活保護世帯へ 3.4倍に拡大 高齢者世帯の27.8%が危機
18年後562万世帯が生活保護世帯へ 3.4倍に拡大 高齢者世帯の27.8%が危機
スポンサード リンク
低賃金の非正規雇用を拡大し続ければ、税収・年金・健康保険料の徴収額が減り続け、非正規で就労して高齢者になった人たちは、蓄えも限られ、年金受領額も少なく、病気などすれば、瞬く間に生活保護を受けるしかない。
そうした心配が、今の国民に蔓延しており、消費不況の原因となっている。
日本総合研究所(日本総研)が国の人口推計や消費に関する実態調査などのデータを基にまとめた。
それによると、18年後の2035年には、収入が生活保護の水準を下回り、貯蓄が不足して平均寿命まで生活水準を維持できない「生活困窮世帯」が、394万世帯余りに上るとしている。
また、平均寿命を超えたり、病気で入院したりした場合に、生活保護の水準を維持できなくなるおそれがある、いわゆる予備軍は167万世帯余りに上り、これらを合わせると約562万世帯となり、高齢者世帯の27.8%を占めるとしている。
生活困窮世帯すべてに生活保護を支給した場合の給付額は、2015年度の約1兆8千億円から、4.9倍に当たる8兆7千億円に増加するという。
日本総研調査部は「バブルの崩壊やリーマンショックなどで老後の蓄えができなかった人が少なくないと見られる。国は、社会保障だけではなく、定年の延長や就労支援など、高齢者の収入確保に取り組む必要がある」と指摘している。
|
平成29年2月現在/厚労省
|
||
|
生活保護世帯
|
構成比
|
|
|
高齢者世帯
|
839,073
|
51.4%
|
|
うち単身
|
761,670
|
46.7%
|
|
うち2人以上
|
77,403
|
4.7%
|
|
高齢者世帯除く
|
791,784
|
48.6%
|
|
うち傷病者・障害者世帯
|
426,876
|
26.4%
|
|
うち母子家庭
|
99,229
|
6.1%
|
|
うちその他
|
262,679
|
16.1%
|
|
総数
|
1,630,857
|
|
|
生活保護者数
|
||
|
2,141,881人
|
||
[ 2017年5月22日 ]



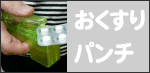




 いま建設業界の求人が急増中、当サイトおすすめの
いま建設業界の求人が急増中、当サイトおすすめの


コメントをどうぞ