 虚空を斬るだけの「沖縄差別論」 -- 安田浩一氏の「沖縄二紙擁護論」をめぐって
虚空を斬るだけの「沖縄差別論」 -- 安田浩一氏の「沖縄二紙擁護論」をめぐって
ジャーナリストと称する安田浩一氏は沖縄が差別されていると主張し、沖縄2紙とタッグを組んで、沖縄差別論を既成事実化したいようだが、少なくとも私が知ってる沖縄県民というかウチナーンチュで、差別されてると思ってるウチナーンチュは一人もいません。
私の子供達(娘2人、息子2人・孫9人)はみな生粋のウチナーンチュですが、誰一人も差別なんてされてません。
ウチナーンチュの子を持つ親として、沖縄をこよなく愛する者として、安田浩一氏等が主張する「沖縄差別論」には心底腹立たしいし、迷惑です。
子供たちや孫達の未来を奪わないでください。
きょうは、篠原 章 さんの「虚空を斬るだけの「沖縄差別論」 — 安田浩一氏の「沖縄二紙擁護論」をめぐって」を紹介します。
篠原 章
https://www.facebook.com/akira.shinohara1?hc_ref=NEWSFEED&fref=nf
批評.COM
http://hi-hyou.com/archives/6071
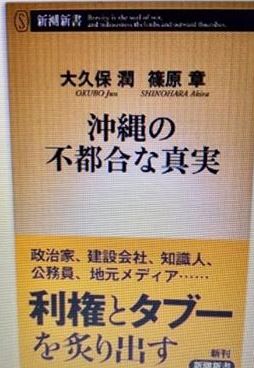
2017/03/05
–Summary–
虚空を斬るだけの「沖縄差別論」 — 安田浩一氏の「沖縄二紙擁護論」をめぐって
「沖縄二紙は偏向している」という琉球新報、沖縄タイムスに向けられた批判に反駁するため、安田浩一氏は『沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか』
(2016年6月)を出版し、「沖縄二紙は偏向してない」と主張している。
安田氏によれば沖縄二紙の論調の土台には「沖縄差別論」があるという。
だが、この沖縄差別論には実体が乏しい。
虚空を斬るようなものだ。
基地問題を観念の世界に追いやり、現実的な解決を難しくしているだけだ。
また、二紙は(この虚空の)沖縄差別論を是としない論調を紙面から排除しているが、こうした言論空間の歪みが半数に近い沖縄県民に大きなフラストレーションをもたらし、県民を分断しかねない状況を招いている。
二紙を擁護する安田氏だが、翁長知事の姿勢と同様、安田氏の議論も偏狭な沖縄ナショナリズムを煽るだけで、基地問題の解決を遠のかせるだけだ。
【はじめに—沖縄二紙批判をめぐる賛否】
「沖縄二紙は偏向している」と批判されるようになって数年が経ちました。
ご承知のように、二紙とは日刊の地方紙「琉球新報」と「沖縄タイムス」のことです。
簡潔にいえば、米軍基地問題についての報道が「基地反対」の立場に肩入れしすぎているというのが、二紙批判の骨子です。
一昨年、人気作家の百田尚樹が、自民党の一会合の席で「沖縄二紙はつぶさなあかん」と発言したことが大々的に報じられ、沖縄二紙批判が俄然注目を集めるようになりました。
このような「風潮」に対する二紙の反発にも根強いものがあり、二紙の応援団も登場しています。
たとえば、基地反対運動を熱心に支援する安田氏浩一氏は、『沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか』(朝日新聞出版・2016年6月30日)と題する著作を出版して沖縄二紙を積極的に応援しています。ここではこの著作を中心に話を進めてみたいと思います。
安田氏は『ネットと愛国 「在特会」の闇を追いかけて』(講談社・2012年)で講談社ノンフィクション賞を、「ルポ 外国人『隷属』労働者」(『G2』Vol.17・2015年)で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞したジャーナリストです。
主要メディアがあまり伝えない「社会的弱者」を取り上げ、その実態を克明にルポルタージュしながら、彼らを弱者の地位に追いやり、彼らを抑圧する社会的・政治的構造を批判する、というのが安田氏の主たるアプローチです。出版界での評価は高いようですが、最近では政治活動家としての側面も強めています。
安田氏が沖縄をフィールドワークの対象にしていると知ったのは、翁長雄志沖縄県知事による国連人権理事会(ジュネーブ)でのスピーチを現地取材したという事実が伝えられたからでした(2015年9月)。
帰国した安田氏は翁長知事のスピーチを評価するレポートを書き、そして本書を執筆しましたが、「沖縄県民は差別されている」とするステレオタイプなアプローチをとっていることに大きな「違和感」を抱きました。
「在日差別」の方程式を沖縄に応用するかのような安田氏の姿勢には、沖縄と基地問題に対する洞察力と想像力が欠けています。
何よりも安田氏が同調する「(構造的)沖縄差別論」の脆さが気になりました。
【実体の乏しい「沖縄差別論」】
『沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか』の大きな特長は、琉球新報と沖縄タイムスで活動する(あるいは活動してきた)多数の記者にインタビューを試みているところです。
そのなかには若手もベテランもいますが、「沖縄二紙は偏向している」という主張に対する彼らの「生の声」を知る良い機会にはなりました。
記者たちの姿勢は、「基地問題とは何か」という安田氏の問いに対して普久原均氏(琉球新報論説副委員長)が即答したという「人権問題ですよ」という言葉のなかに集約されているようです(90頁)。
記者たちのあいだでは、「日本(人)は沖縄(人)を差別している」という意識が広く共有されているということになります。
本書で展開されるのは、この「加害者(差別者)=日本人、被害者(被差別者)=沖縄人」という構図に沿った「物語」です。
こうした「沖縄差別論」を「唯一絶対のもの」として受け入れる人びとは、本書を「すぐれたルポルタージュ」と評価するかもしれません。
彼らの立場に立てば、被差別者・沖縄人を代弁して差別者・日本人を糾弾し続ける沖縄二紙の「正当性」は揺るぎのないものとなり、二紙は「正義」のメディアということになるでしょう。
が、そもそも「沖縄差別論」に実体はあるのか、という疑問が湧いてきます。
これについては小著『沖縄の不都合な真実』(新潮新書・2015年1月・大久保潤との共著)で詳しく書きました。
そこでは、「沖縄差別論」は、沖縄内部の問題点や矛盾を覆い隠すための「装置」あるいは「装飾」だという見解を述べています。
本稿では「政治的リアリズム」の観点から、「沖縄差別論」は虚空を斬るような議論であることを明らかにしたいと思います。
「沖縄差別論」を唱える人たちは、「米軍基地の押しつけ」が沖縄差別だといいます。
その象徴となっているのが「辺野古移設」です。
米軍基地が沖縄に偏在しているという事実はまちがいありません。
それが地域の負担となっていることも周知の通りです。
沖縄に基地が置かれている現状は地理的・政治的・歴史的な産物です。
その歴史の総体を「差別・被差別」という視点で読み解こうとするのが「沖縄差別論」の方法論です。
この論に与する人びとは、基地の押しつけは「日本の民主主義」が、沖縄を差別的に扱った歴史的帰結であるから、その民主主義を支える「日本人」すべてが加害者であるという主張を展開します。
しかしながら、たとえば辺野古移設をめぐる経緯を観察するには、「加害者」「被害者」という見方とは違った視点が求められます。
辺野古移設が、1995年の少女暴行事件に端を発することは誰でも知っています。
事件を受けて県民運動が盛り上がった結果、日米トップの合意で普天間飛行場の返還が劇的に決まりました。
1996年には日米政府の協議機関SACO( 沖縄に関する特別行動委員会)の最終報告が出され、嘉手納以南の米軍施設を中心とする整理縮小計画が決まりました。
その後、普天間飛行場の名護市辺野古への移設が決まりましたが、SACO報告から21年経ってもまだ普天間飛行場は同じ場所にあります。
移設先の名護市の事情と、反対運動の圧力、反対運動や県民に対する政府と沖縄県の対応の失敗などが、移設が進まない主な理由です。
政府(日本・日本人)だけが辺野古移設の経緯に責任を負うかのような論調が強いのですが、以下のような経緯があったことは確認しておかなければなりません。
(1)沖縄県、名護市とも政府・米軍と辺野古移設について合意した経緯がある。その意味で辺野古移設は四者納得の上で実現したものだ。
(2)にもかかわらず、施設の位置や設計について長期にわたってもめたが、主たる原因は沖縄側の調整(業者間の調整など)が難航したことによる。
(3)最終的に辺野古沿岸を埋め立て2本の滑走路の造成を求めたのは沖縄側である。
(4)地元・辺野古は移設を事実上容認している。
こうした経緯を知ると、政府批判にだけ正当性・合理性があるとは思えません。
「沖縄差別論」では解釈不能なプロセスです。
被差別者(被害者)・差別者(加害者)が渾然一体となっています。
いったい誰が被差別者で、誰が差別者なのでしょうか。
しばしば「政府による押しつけ」の圧力に屈して沖縄は無理矢理承服させられたのだ、という反駁がありますが、安全保障という公共財の配分について、政府と協議の上自治体側が施設を受け入れたプロセスを「差別」と呼んで非難するなら、それは住民や国民の暮らしを守るという国の役割を否定することになり、無秩序の肯定につながります。
ただし、その後、名護市長や沖縄県知事が替わって、「沖縄の民意」に変化が起きたことは間違いありませんが、民意だけを問題とするなら、「辺野古の民意」はどう評価すればいいのでしょうか。
加えて政府の側の行動にも正当性はあります。
何よりも前提となるのは当初の政策目標です。
重視しなければならないのは、普天間飛行場の移設は基地の整理縮小計画の一環であるという点です。
また、SACO報告に基づく整理縮小計画が最初で最後の計画だなどとは誰もいっていません。
整理縮小はまだまだ継続します。
いってみればある種の出発点にすぎません。
日米の安全保障政策を見据えながら、整理縮小は今後も続ける必要があります。
ところが、その出発点でつまずいているのというのが実情です。
普天間飛行場を「県外移設せよ」との声は今も根強く残っていますが、基地縮小計画に「理想」や「理念」をぶつけるだけでは前に進めません。
「時間軸」を無視した議論は住民の命を脅威に晒します。
沖縄差別論から派生した「基地引き取り」運動も、関係者の意図がどうであれあまりにも非現実的で、解決の時間をいたずらに引き延ばすだけの愚行です。
「引き取り」の議論を進めるためには、米軍・自衛隊・安全保障に関する知見に加えて、引き取りの場所の選定、住民や行政の説得や地権者の了解、各種法規・条例との整合性、環境アセスメントの実施、議会の承認など無数の「手続き」に直面します。
これをクリアするための時間の問題も大きな課題です。引き取り運動の現状を見ると、その覚悟があるとはとても思えません。
現実は、利権・既得権・関係者の政治的立場や理念が絡みあいながら動いています。
それがこの世界のダイナミズムであり、厄介さでもありますが、そこからは逃れようがありません。
「沖縄差別論」はこうした「厄介さ」を意図的に無視または回避して、思考の枠組みのなかに現実を押し込もうとするものだと思います。
「構造的差別」の存否などを問題にしても不毛な議論が続くだけで、けっして前に進みません。
「沖縄差別論」は現実から乖離した、ある種の虚構を問題とする議論にすぎないと思います。
私も辺野古移設には反対です。
立地にも経費にも問題があると思います。が、様々な利害や判断が重なって生まれた結論が辺野古移設だったのですから、それを実力で阻止しようとは思いません。
民主主義的な決定を実力行使で覆すことができるとすれば、民主主義など何の価値もなくなります。もちろん、この民主主義には沖縄も含まれています。
繰り返しになりますが、「移設反対」の実力行使によって移設作業が遅滞し、人口密集地にある普天間基地が温存されることは、「住民のいのちを守る」という観点から大問題です。
昨年12月、復帰以来最大の基地縮小となる北部訓練場の過半がようやく返還されましたが、「基地反対」を唱える人びとは、ヘリパッド移設を理由に返還自体を糾弾する抗議行動に訴えました。
事実上「返還」を否定する行動だったといっていいでしょう。
今や「基地反対」のリーダーとなった翁長知事は返還式典への出席を拒絶し、直前に発生したオスプレイの事故を問題視する集会に出席しました。
翁長知事はそこで「沖縄差別」を糾弾するかのようなメッセージを発し、返還による基地の縮小には一言も触れませんでした。
「基地縮小」など眼中にないかのような振る舞いだと思います。
基地縮小を前向きに受けとめない「基地反対」など、「基地縮小反対」の誹りを免れません。
あらためて強調しましょう。
沖縄の米軍基地問題における最大の課題は「基地を減らすこと」です。
この点を忘れて辺野古移設の正当性をめぐる議論はできません。
「日米合意による基地縮小では不十分だ」という主張は理解できます。
だからといって現行計画を否定し、基地縮小プロセスをひたすら遅滞させるような実力行使が認められるものではありません。
SACO報告による縮小を迅速に進めていれば、今頃SACO報告に続く第2、第3の縮小プログラムが示されていたでしょう。
なんと無駄な年月をすごしたのかと思いますが、今さら過去に拘っていてもしょうがありません。
確かにこれまでの政府の取り組みも不十分でしたが、沖縄県や基地反対運動の対応にも多くの問題があったことは事実です。
つまり、基地縮小がこのように遅滞しているのは日本と沖縄の共同責任なのです。
ここでは詳しく論じませんが、もっとはっきりいえば、基地縮小が容易に達成できないのは、「基地反対」を沖縄振興策維持・増額のための圧力に利用する経済的・社会的構造が存在するからだと思っています。
政府と沖縄の共犯関係において維持されている沖縄振興策こそ最大の「ガン」です。沖縄振興策について触れもしない「沖縄差別論」は、貧困などといった沖縄が抱える深刻な経済的・社会的問題を覆い隠す装置として機能するだけです。
「沖縄差別論」をいくら熱心に唱えても病巣はけっして取り除けません。
むしろ「沖縄差別論」をきっかけに台頭しつつある「沖縄ナショナリズム」とそれに対抗する「日本ナショナリズム」との不毛な闘いが深刻化し、事態はますます悪化するだけです。
【言論空間の歪みをもたらす沖縄二紙】
ここで百歩譲って「沖縄差別論」という虚論の発信を認めるとしても、沖縄二紙のあり方は正当化できません。
沖縄県民すべてが「加害者(差別者)=日本人、被害者(被差別者)=沖縄人」という構図を受け入れているわけではないからです。
日本人の一員として政府の安保政策を受け入れる、あるいは支持する県民が多数存在します。
ところが、県内でそうした保守層の存在を伝える新聞は石垣島で発行される八重山日報だけです。
これに比較的中立的な宮古毎日新聞(宮古島)を加えることもできますが、いずれも離島で発行される日刊紙であり、人口の大部分が集中する沖縄本島(人口約130万人)で発行されているのは、事実上、琉球新報(16万部)と沖縄タイムス(同前)の二紙だけということになります。
本土の新聞も入手できますが、事業所やホテルなどで購読される日本経済新聞(6000部)が目立つだけで、他紙は1000部にも届きません。
政府の安保政策を受け入れる、あるいは支持する沖縄県民が存在することを伝える新聞メディアは事実上存在しないのです。
沖縄二紙の「県内世論における支配的なポジション」が、全国紙や通信社、NHKを始めとする全国ネットのテレビ局の報道のあり方に影響を与え、基地問題に対する言論空間を特定の方向に誘導することになっている傾向は否めません。
こうした現状を踏まえると、沖縄二紙の基地報道を「正義」と捉えない沖縄県民が二紙による基地報道のあり方を批判するのはきわめて自然なことです。
二紙にフラストレーションを抱く保守層から、「琉球新報、沖縄タイムスを正す県民・国民の会」(我那覇真子・代表運営委員)が登場したのも当然のことでしょう。
同会は、ネットや人的つながりを駆使して「沖縄二紙の偏向」を訴える活動を展開しており、同会の活動に背中を押されて、八重山日報が沖縄本島での発行を計画するまでになっています。
百田尚樹氏や櫻井よしこ氏など本土の保守層からも同会の活動を高く支持する識者も登場していますが、「正す会」はなにも「二紙をつぶす」と息巻いているわけではありません。
会称どおり「二紙を正す」ことが目的です。
「沖縄差別」という考え方に同意しない同会が、「二紙がいうような沖縄差別は存在しない」と主張するのも妨げられるべきことではありません。
彼らの運動は「二紙は沖縄にも多様な意見・見方が存在することを認めた編集方針をとれ」といっているのであって、「我々の考え方こそ唯一の正義なのだから二紙は我々に従え」などと強要しているわけでもありません。
批判的活動としてはきわめて真っ当だと思います。
同会に同調してネット上に過激とも取れる書き込みや言説が存在することも確かです。
その一部は、沖縄二紙をまともに読んだこともない、沖縄を訪れたこともない本土の人間から発せられています。
だからといって安田氏のように、沖縄二紙批判が沖縄に対するヘイトスピーチの温床であるかのように批判する姿勢には大いに問題があるといえるでしょう。
「沖縄差別」を喧伝する沖縄二紙にも言論の自由はありますが、二紙批判にもれっきとした言論の自由はあります。
安田氏も、保守層に傾斜した報道を主とする八重山日報のあり方には一定の存在意義を認めています。
八重山日報の存在意義を認めるなら、沖縄二紙に対する批判者の存在意義を認めてしかるべきでしょう。
「沖縄二紙に正義がある」という言論に対して「沖縄二紙に正義はない」という言論が対置されることに、自由な言論を保障するこの民主主義社会でなんの不都合があるのでしょうか。
もちろん、私も「沖縄二紙の基地報道は偏向している」と考えています。
市場で激しい競合関係にある沖縄二紙が、こと米軍基地問題になると、スポーツ紙と見紛う巨大な見出しを掲げ、どちらの新聞かほとんど区別がつかない政府批判記事・米軍批判記事で埋め尽くされることにいつも驚愕しますが、「二紙が偏向している」と思うのは必ずしもそうしたポイントではありません。
彼らがジャーナリズムとして、あるいはメディア・ビジネスとして、反政府・反権力の姿勢を社是のようなものにしていることを理解するとしても、県民のなかにある、基地問題に対する多様な意見・見方を無視したかのような紙面構成には強く異議を申し立てたいと考えます。
二紙の紙面に登場するのは「基地反対」の姿勢が明確な県民や本土の識者ばかりで、「基地容認」の声はほとんど伝わってきません。
社の方針がたとえ「基地反対」「翁長知事支持」「反対運動支援」だとしても、県民のなかに「基地容認」「翁長知事批判」「反対運動批判」の声があることを認めない紙面構成は尋常ではないと思います。
朝日新聞やNHKですら、「沖縄は基地反対だけではない」という実情をしばしば伝えています。
沖縄二紙にフラストレーションを感ずる県民が少数派(といっても県民の40%〜45%相当にあたる)だからといって、その存在を無視したかのような報道姿勢が許されるのでしょうか。「沖縄人は差別されている」という論調だけが紙面を支配すればよいのでしょうか。沖縄二紙の「報道しない自由」は、沖縄に関する言論空間を明らかに歪めています。異論封殺の常態化は、県民を分断するだけです。
これに関連していえば、2015年2月より約1年間にわたって沖縄県内主要書店でベストセラーを続けた小著『沖縄の不都合な真実』に対して、琉球新報は、2015年の8月19日、20日の二日にわたり『沖縄「真実」本 差別隠蔽の論法』(2015年⑻月19日:桃原一彦執筆/同20日:池田緑執筆)と題する記事を掲載し、厳しい批判を展開したました。そこでは、私たちの主張は「ヘイトスピーチ」として断罪されたのです。
このような一方的な批判に対して、篠原と共著者・大久保潤の両名は、琉球新報社に対して反論の機会を与えるよう数か月にわたって交渉し、許しを得て反論原稿も編集部に送付しましたが、以後「なしのつぶて」となりました。社の方針にそぐわないからといって、厳しく批判を加えた相手に反論の機会を与えない言論機関など、言論の自由を語る資格はありません。一方、沖縄タイムスは、本書がベストセラーであることをランキング記事で伝えながら、書評も批判も一切掲載しませんでした。完全なる黙殺です。これもまた自分たちに都合の悪いものは取り上げないという姿勢の典型だと思います。要するに「沖縄二紙が尊重するのは『報道の自由』ではなく『報道しない自由』なのか」と揶揄したくなるような対応ばかりだったということです。二紙のこうした対応を「歪んでいる」と批判して何が問題なのでしょう。
それだけではありません。安田氏は「日本における民族主義の台頭」が沖縄に対するヘイトスピーチを生みだしているといいますが、その一方で琉球新報の紙面に掲載される「沖縄(琉球)ナショナリズム」としかいいようのない排外主義的な記事に対して批判を加えません。沖縄県民を「少数民族」と見なし、その救済を訴えるかのような翁長知事の国連スピーチなど、「少数民族尊重」に名を借りた排外主義の発露にすぎませんが、それを評価する安田氏の論法もまた「偏狭なナショナリズムの台頭」を煽るだけです。まともな人権主義者・平和主義者なら、「民族の問題」(「血の問題」)が持ち出されたときにこそもっとも警戒すべきなのに、安田氏はその警戒心をすっかり失っているのです。
あらたな差別やヘイトスピーチさえ生みだしかねない「沖縄差別論」を信奉する現在の沖縄二紙など擁護するに値しません。彼らが自分たちと異なる他者の言論に対して開かれない限り、沖縄の言論空間の歪みはけっして正されないと断言してもいいでしょう。
参考:安田浩一『沖縄の新聞は本当に「偏向」しているのか』朝日新聞出版・2016年6月30日・\1,400(税抜)




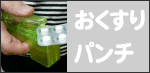








コメントをどうぞ