 小保方晴子女史STAP万能細胞はどうなってるの?
小保方晴子女史STAP万能細胞はどうなってるの?
猿どころかヤギの実験に取り掛かっているハーバード
STAP万能細胞の製造は、理研 発生・再生科学総合研究センター細胞リプログラミング研究ユニットの小保方晴子研究ユニットリーダーを中心とする研究ユニットと同研究センターの若山照彦 元チームリーダー(現 山梨大学教授)、および米国ハーバード大学のチャールズ・バカンティ教授らの共同研究グループによる成果としている。
マウス実験により、成功したとされているが、今後ヒトへの試験へ順次移行していく。
ところが、米国ハーバード大学のチャールズ・バカンティ教授らは、すでにマウスどころか2011年から猿でのSTAP万能細胞作成試験を始めているとし、更に現在ではヤギでの試験を行っているという。
小保方晴子女史は、マウスによるSTAP万能細胞の製造に成功したが、公開論文には日付を発表していない。2008年に半年間ハーバード大に留学、その時、チャールズ・バカンティ教授に師事し、STAP多能細胞を発案したとされる。
バカンティ教授の助言を得て、極細のガラス管を使ってマウスの脳や皮膚などさまざまな細胞から幹細胞を取り出す実験を進めた。すると想定以上の幹細胞を取り出すことができた。細胞は、細い管を通ることでストレスを受け、いろいろな細胞に変化する以前の幹細胞に戻っていたという。しかし、バラ付きが多く安定しなかったとされる。
その後、小保方晴子女史は大学院へ戻り、2011年から理研へ、そこで、当時チームリーダーの若山照彦氏(現山梨大教授)が加わり、刺激・ストレスに酸性の溶液を用いたことにより、刺激惹起性多能性獲得細胞(STAP幹細胞)が、安定的に発現したという。
なお、特許は日米3機関合同で出願済み。
STAP万能細胞については、日本ではマウス段階のようだが、すでに実際の研究ではハーバード大学が先行し、2011年から猿による試験、現在ではヤギによる試験も行っている。
<STAP細胞発表に触発された新日本科学株>
新日本科学は、1000匹の実験用猿を有しているが、基幹事業とする非臨床試験受託事業で培ったノウハウを活用し、アストリムが取り組んでいる人工多能性幹細胞(iPS細胞) 技術を適用した新たな免疫細胞療法の研究開発、早期の臨床応用・実用化を支援するとし、240万円(3.9%)出資すると1月31日発表した。
アストリムは、京都大学再生医科学研究所の河本宏教授および京都大学 iPS 細胞研究所(CiRA)の金子新准教授の発明によるT細胞を再生する(若く元気な細胞を分化誘導する)技術をもとに設立された日本発のベンチャーとして知られる。
新日本科学の株価は1月30日棒上げ、1月31日ストップ高となっている。
試験用猿の新日本科学の本拠地は鹿児島指宿、山村教授の試験用マウスのトランスジェニックの本拠地は熊本にある。
小保方晴子女史も間接的にトランスJ、新日本科学の生き物のお世話になる。

モバイル向けURL http://n-seikei.jp/mobile/








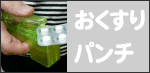










コメント