 住宅市場:注文住宅の減少続く、2014年の着工は大震災年を下回る予想
住宅市場:注文住宅の減少続く、2014年の着工は大震災年を下回る予想
2013年の住宅業界はアベノミクス経済と消費税増税前の駆け込み需要でバブル的な活況を見せた。ここ2年総着工戸数の35%前後占めてきた注文住宅(持家)も、今年に限っては、消費税増税の影響を受け、大きく落ち込み、全着工比率に占める割合も32%まで減じている。
これは、戸建の自宅を、新築や改築をする人が、大幅に減少していることによるもの。
住宅産業は、経済波及効果が大きくGDPに与える影響も大きい。(全住宅着工戸数の1~10月累計は737千戸、前年は798千戸であったこことから今年は▲8.7%減じている)
しかも、注文住宅=戸建業界は、昨年は一時的に酔いしれたものの、今年は奈落の底に突き落とされた格好となっている。このままでは、これまで長年続いた30万戸の大台さえも割り込むことが予想される。それほど、消費税増税のインパクトは消費者に大きな打撃を生じさせている。当然駆け込み需要の反動と見ることもできるが、注文住宅の着工戸数は、駆け込み需要数以上に減じているのが気がかりだ。こうした状況は12月まで続き、1月は最近3ヶ月の着工戸数である2万4千戸台まで今年1月の着工数が落ち込むため、前年同月比レベルで、マイナス幅は少なくなると見られる。
今のところ、アベノミクス効果は、消費税増税前の駆け込み需要によるあらゆる分野で押し上げ効果はあったものの、増税後の落ち込みはそれ以上に大きく、また、さらなる大円安政策により国内市場は今後物価高に見舞われ、実質可処分所得が減じる中、さらに減じる可能性を秘めている。消費増による経済成長は当分、見込めないものかもしれない。
いっそのこと、欧州並みに同一労働同一賃金にするか、最低賃金の時給を全国一律1000円に、三大都市圏は1200円にでもしなければ、公務員と大企業ばかり報酬が上がっても、全体の消費経済は前を向かないものと思われる。中小企業の勤労者や非正規雇用者と公務員との賃金格差は拡大するばかりとなる。
もしも、実現できれば、少子化にも歯止めがかかり、消費も増え、住宅投資も増加するというものだろう。さらに、大手企業の従業員にとってもいつ首になるかわからない時世であり、住宅投資の色の濃い潜在顧客であるものの、まずは職の安定・収入の安定がそうした国民の不安心理を和らげ、住宅投資も復活してくるものと思われる。私腹を肥やす政治家による待機児童問題などは論外だ。
|
注文住宅の着工戸数月別推移/数値は国交省発表分
|
||||||
|
|
2012年
|
2013年
|
2014年
|
|||
|
|
|
対前年
|
|
対前年
|
|
対前年
|
|
月
|
戸数
|
同月比
|
戸数
|
同月比
|
戸数
|
同月比
|
|
1
|
21,687
|
-2.7
|
23,561
|
8.6
|
24,955
|
5.9
|
|
2
|
22,462
|
1.5
|
22,987
|
2.3
|
22,891
|
-0.4
|
|
3
|
22,335
|
-2.3
|
24,879
|
11.4
|
21,650
|
-13.0
|
|
4
|
24,137
|
2.5
|
28,357
|
17.5
|
23,799
|
-16.1
|
|
5
|
25,468
|
8.2
|
28,902
|
13.5
|
22,288
|
-22.9
|
|
6
|
26,971
|
0.1
|
30,699
|
13.8
|
24,864
|
-19.0
|
|
1~6
|
143,060
|
1.2
|
159,385
|
11.4
|
140,447
|
-11.9
|
|
7
|
28,338
|
-12.5
|
31,475
|
11.1
|
23,524
|
-25.3
|
|
8
|
28,208
|
-9.1
|
31,379
|
11.2
|
24,250
|
-22.7
|
|
9
|
28,125
|
12.6
|
32,128
|
14.2
|
24,617
|
-23.4
|
|
10
|
28,894
|
13.0
|
33,967
|
17.6
|
24,245
|
-28.6
|
|
1~10
|
256,625
|
0.5
|
288,334
|
12.3
|
237,083
|
-17.8
|
|
11
|
28,216
|
9.2
|
34,580
|
22.6
|
|
|
|
12
|
26,748
|
9.2
|
31,858
|
19.1
|
|
|
|
7~12
|
168,529
|
2.5
|
195,387
|
15.9
|
|
|
|
年計
|
311,589
|
1.9
|
354,772
|
13.9%
|
|
|
|
|
全着工戸数
|
注文住宅
|
注文住宅の占有率
|
備考
|
|
2010年
|
813,126
|
305,195
|
37.5%
|
リーマンショック余韻
|
|
2011年
|
834,117
|
305,626
|
36.6%
|
3月11日大震災
|
|
前年比
|
2.5%
|
0.1%
|
|
|
|
2012年
|
882,797
|
311,589
|
35.3%
|
12月末安部政権誕生
|
|
前年比
|
5.9%
|
1.9%
|
|
|
|
2013年
|
980,025
|
354,772
|
36.2%
|
4月日銀大緩和
|
|
前年比
|
11.0%
|
13.8%
|
|
|
|
2014年(10月迄)
|
737,481
|
237,083
|
32.1%
|
4月消費税増税
|
|
前年比
|
-7.7%
|
-17.8%
|
|
10月迄の累計比
|
|
ここ3ヶ月の注文住宅の着工件数
|
||||||
|
|
2014年8月
|
2014年9月
|
2014年10月
|
|||
|
北海道
|
1,138
|
-14.6
|
984
|
-28.8
|
1,012
|
-26.0
|
|
東北
|
2,471
|
-20.5
|
2,436
|
-23.6
|
2,364
|
-27.1
|
|
関東
|
7,946
|
-23.4
|
7,795
|
-22.3
|
7,718
|
-28.2
|
|
北陸
|
1,385
|
-25.8
|
1,347
|
-37.5
|
1,307
|
-39.5
|
|
中部
|
3,415
|
-27.1
|
3,904
|
-20.4
|
3,847
|
-26.6
|
|
近畿
|
2,924
|
-19.5
|
3,005
|
-19.0
|
2,863
|
-29.6
|
|
中国
|
1,399
|
-22.1
|
1,389
|
-29.9
|
1,475
|
-34.4
|
|
四国
|
919
|
-13.4
|
854
|
-25.3
|
879
|
-34.5
|
|
九州
|
2,432
|
-23.6
|
2,656
|
-17.0
|
2,526
|
-19.6
|
|
沖縄
|
221
|
-35.2
|
247
|
-41.9
|
254
|
-38.3
|
|
合 計
|
24,250
|
-22.7
|
24,617
|
-23.4
|
24,245
|
-28.6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上記期間の2013年は
|
||||||
|
|
2013年8月
|
2013年9月
|
2013年10月
|
|||
|
北海道
|
1,332
|
6.1
|
1,382
|
6.9
|
1,368
|
17.3
|
|
東北
|
3,110
|
15.6
|
3,189
|
8.7
|
3,242
|
14.3
|
|
関東
|
10,371
|
7.2
|
10,036
|
6.5
|
10,744
|
13.1
|
|
北陸
|
1,867
|
17.9
|
2,156
|
48.3
|
2,159
|
45.5
|
|
中部
|
4,686
|
8.9
|
4,904
|
19.3
|
5,241
|
15.4
|
|
近畿
|
3,634
|
12.8
|
3,712
|
14.1
|
4,069
|
15.0
|
|
中国
|
1,795
|
21.0
|
1,981
|
24.0
|
2,249
|
41.2
|
|
四国
|
1,061
|
15.6
|
1,143
|
14.8
|
1,342
|
17.0
|
|
九州
|
3,182
|
15.2
|
3,200
|
16.5
|
3,141
|
14.1
|
|
沖縄
|
341
|
9.3
|
425
|
32.4
|
412
|
22.3
|
|
合 計
|
31,379
|
11.2
|
32,128
|
14.2
|
33,967
|
17.6
|
|
・8~10月の3ヶ月間比較では今年は前年に比し ▲25%減少している。
|
||||||
<投資家の動向と住宅投資>
株価が上がれば、企業は儲かり、投資家により消費も全体を押し上げるという論法は、些か強引だ。確かに、昨年の安部政権誕生に続く日銀黒田丸による金融大緩和策により、65.4%もの株価上昇は、百貨店の売上高、特に高額商品中心に増加し回復した。しかし、4月の消費税増税後は鳴かず飛ばずの状況に再び陥っている。
10月31日、国は、第二次大緩和策と年金の株投資枠倍増を打ち出し、株価を急騰させたが、このW施策のインパクトは1ヶ月後までに11.5%の株価上昇しか見ていない。
政権が期待する株高による消費増は、年末商戦を見ない限りわからないが、前回のように百貨店の売上高を回復させるまでの原動力になるとは到底思われない。上昇率11.5%の率は、乱高下する株市場において、通常ありうる指数でもある。また、日本の株価だけ上がる要素も米国を除き低迷する世界経済にあり望みは少なく、第一次のような上がり方はまったく期待できない状況といえる。外資はアベノミクス音頭で踊ってはおらず、日本人投資家のようにバブル化していない。日本の財政規律問題を常に念頭に置き、売り買いを交錯させながら、日本の株式市場で稼ぎまくっているのが実情だ。
そうした中、投資家が今の株価上昇率で住宅などの消費=投資に回す可能性は低いと見られる。
ただ、日本には、詐欺に数千万も盗られるような大金持ちも多く、こうした人たちが積極的に、住宅投資などに資金を回せば、明るさも次第に見えてこよう。
世の中、翼の折れたエンゼルにならないでもらいたいものだ。
|
第一次上昇
|
上昇率
|
|
|
|
日経平均
|
|
|
2012年11月30日
|
9,446.01
|
|
|
2013年5月22日
|
15,627.26
|
65.4%
|
|
第二次上昇
|
上昇率
|
|
|
2014年10月30日
|
15,658.20
|
|
|
2014年11月28日
|
17,459.85
|
11.5%
|

<ターゲットは公務員?>
維新の橋下氏が首相にでもならない限り、公務員(正社員)の報酬は減るどころか増加する一方である。今回の人事院の給与増勧告も大昔のように4月にさかのぼって実施される。
公務員は組合のご加護もあり、リストラも行われない。それどころか非正規雇用まで含めると国や地方公共団体は大幅に増員しているのが実情だ。
こうしたことから、住宅営業は、大手企業の社員は当然のことながら、公務員共済組合に裏金をばら撒き、公務員を営業ターゲットにするのも賢いやり方ではないだろうか。







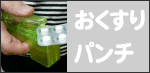







コメントをどうぞ