 トマ・ピケティ「21世紀の資本」書評一覧 ビル・ゲイツほか
トマ・ピケティ「21世紀の資本」書評一覧 ビル・ゲイツほか
「21世紀の資本」/みすず書房・5940円/Thomas Piketty 71年生、フランス生まれ。パリ経済学校教授。
<ビル・ゲイツ評・・・対談>
フランスの経済学者トマ・ピケティ氏は、世界一の富豪から、2014年に出版され世界的に話題になっている著書『21世紀の資本』に深く共感すると言われたという。ただし、富裕層に増税することを除いてだそうだ。
ブ ルームバーグの記事によると、ピケティ氏は1月3日にボストンで開催されたカンファレンスで、マイクロソフトの共同創業者で今でも世界長者番付で首位を維 持しているビル・ゲイツ氏から、「あなたの本に書かれていることすべてに賛成だが、これ以上税金を払いたくはない」と言われたことを明らかにした。
それは、ゲイツ氏は慈善活動家として自らの資金を使う方が、「政府に支払うよりもより効果的に」使えると考えているからだという。
パリ経済学校で教授を務めるピケティ氏は、「たしかに、彼ならば(政府より効果的な)時もあるかもしれない」と述べ、慈善活動家のゲイツ氏ならば、政府より良い方法で資金を使うこともあるかもしれないと認めたという。
フィナンシャル・タイムズの2014年の「ビジネス・ブック・オブ・ザ・イヤー」に選ばれた『21世紀の資本』は、富裕層への課税を世界規模で強化して、格差の拡大を抑えるよう訴えている。
ゲイツ氏は、2014年10月に個人ブログで『21世紀の資本』に対する書評を公開しているが、その中で、「格差の拡大は問題である」点や、「資本主義が格差拡大への流れを自己修正することはない」点など、ピケティ氏の「最も重要な結論」の多くに同意すると書いている。
しかしゲイツ氏は、この本の論点のひとつに反論もしている。それは、「『格差の拡大に向かう』という資本主義が本質的にもつ傾向に対抗するには、政府が資本への課税を強化する必要がある」という点だ。
ゲイツ氏は書評の中で、「税制の仕組みが、労働収入への課税から転換するべきという点には賛成だ」としながらも、「しかし、ピケティ氏が提案するように、資本への累進課税に移行するのではなく、消費への累進課税にするのが一番だと思う」と書いている。
ゲイツ氏はピケティ氏が、富める者一人一人が自らの富をどのように使っているかを考慮せずに、富裕層をひとまとめにしている点は間違っていると主張した。そして、例えとして「ひとりは企業に投資し、ひとりは慈善活動に充て、ひとりは贅沢な生活に使っている」3人の富豪を挙げ、「最後のひとりの生活に問題はないが、しかし他の2人より多くの税金を払うべきだと思う」と書いている。
マイクロソフト社での役職を減らして以降、ほぼ慈善活動に専念しているゲイツ氏が、この3人の富豪のうち、自身をどのタイプと考えているかどうかは、想像に難くない。ゲイツ氏は。ゲイツ夫妻が共同で運営している慈善基金団体「ビル&メリンダ・ゲイツ財団」は、1994年の設立以降、総額300億ドル以上の補助金を、飢餓や貧困の撲滅に役立てている。
ゲイツ氏は書評の最後の方で、「慈善活動は、社会問題の解決策の重要な要素になりうる」と書いている。「適切な方法で行われた慈善活動は、社会に直接利点をもたらすだけでなく、世襲財産を減らすことにもなる」
ハフポストUS版では、ビル&メリンダ・ゲイツ財団にメールや電話でコメントを求めたが、記事執筆時点で得られていない。ピケティ氏にもメールで問い合わせたが、まだ回答はない。
<アサヒ・コム>
富の格差鋭く分析、分配問題を核心に
資本主義の格差拡大傾向を鋭く分析した世界的ベストセラーの邦訳版が、ついに出版された。本書は、富の格差や社会階級の問題に関心を失った現代経済学を批判、分配問題を経済分析の核心に戻すと宣言する。これは、19世紀までの古典派経済学が持っていた良質な問題意識の復活でもある。18世紀から21世紀初頭の膨大な各国データで歴史的実証分析を行い、そこから資本主義に内在する傾向法則を掴(つか)み出そうとする。そのタイトルはもちろん、マルクスの『資本論』を意識したものだ。
本書の分析結果が国際的に敬意を払われているのは、ピケティが、「分配論」(第3部)の科学的基礎として「資本蓄積論」(第2部)を、詳細な実証分析に基づいて展開しているからだ。格差拡大傾向の指摘だけなら、本書がここまで影響力をもつことはなかったであろう。彼はまず、20世紀に二つの世界大戦による破壊と、平等化を目指す公共政策の導入で打撃を受けた民間資本の蓄積が1970年以降、本格的に復調してきたことを確かめる。そしてシミュレーションで今世紀末までには、国民所得に対する資本の価値比率(資本/所得比率)が、格差の大きかった19世紀末の水準にまで高まると予測する。
もっとも、資本蓄積が高度に進むと、資本の限界生産性(収益率)が低下するという矛盾が生まれる。だからこそマルクスは、利潤率低下で資本主義は崩壊すると予測した。だが資本主義は、想定以上の柔軟性を発揮し、収益率低下を上回る技術進歩や、より収益性の高い資本用途の発見により、国民所得に占める資本シェアの低下を回避することに成功してきた。
しかし、資本蓄積は別の問題を引き起こす。格差の拡大だ。ピケティの功績の一つは、歴史上ほぼすべての時期で「資本収益率(r)」>「経済成長率(g)」が成立していることを明らかにした点にある。これは、資本の所有者に富を集中させるメカニズムが働いていたということだ。民主化と平等化が相伴って進展した20世紀は、例外的な時期だったと振り返られる可能性すら出てきている。
資本蓄積が高水準に達し、しかも低経済成長レジームに入った21世紀では、新たに付け加えられる富よりも、すでに蓄積された富の影響力が相対的に強まる。これは、「r>g」による格差拡大メカニズムをいっそう増幅させる。ピケティは1980年以降、国民所得に占める相続と贈与の価値比率が増加に転じたことを確認、相続による社会階層の固定化に警告を発する。
だが「r>g」は、20世紀がそうだったように、資本主義に不可避的な経済法則ではない。特に国家による資本(所得)課税のあり方は、資本収益率に決定的な影響を及ぼす。1980年以降、グローバル化で各国間の租税(引き下げ)競争が強まり、資本課税は弱体化してしまったが、ピケティは、国際協調に基づく「グローバル資本税(富裕税)」の導入が不可欠だと強調する。これは、個人が国境を超えて保有する純資産総計への課税だ。その実現は、夢物語ではない。OECDで租税情報の国際的自動交換システムの構築が進展しているからだ。
こうした課税システムは、経済と金融の透明性を向上させ、資本の民主的統制を可能にする。21世紀をどのような世界にするかは結局、市場と国家に関する我々の選択にかかっている。その意味で本書は、格差拡大に関する「運命の書」ではなく、資本主義の民主的制御へ向けた「希望の書」だといえよう。
<フライヤー>
ノーベル経済学賞を受賞したポール・クルーグマンは本書を「今年、そしておそらくこの10年間で最も重要な経済書」と称した。経済格差に関するトマ・ピケティの鋭い洞察は、最初に出版されたフランスだけにとどまらず、世界中で大きな話題を呼んでいる。そしてついにこの話題の書籍の日本語版が発表されたのである。
かつては「一億総中流」といわれた日本でも、近年では格差が広がったと叫ばれることが増えてきている。本書では経済格差の実態を明らかにするとともに、経済格差を埋めるためにはどうすれば良いのか、具体的な施策を提案している。
その理想の実現にはまだまだ遠いかもしれないが、実現に向けた第一ステップは取り組む価値が十分にあるものだ。
700ページを越える大著のため、読むには多少時間が必要かもしれないが、論理構造はストレートで、グラフや分かりやすい統計情報を用いて解説しているため、意外にもあっさり読めてしまうかもしれない。
たとえば、既存の経済学では富の不平等度合いをジニ係数という統計概念を用いて説明することが多いのだが、本書では所得階層別の比率(上位10%が国民所得の何割を稼いでいるか、など)という誰にでもわかる形で表現している。
この本を読む読者の多くは所得階層が上位にいると想定されるが、格差が歴史上で最も広がりつつあるという事実を目にして、自身の富だけでなく、社会全体に目を向けるきっかけにもなるに違いない。
<ほかに>
それじゃピケティは『21世紀の資本論』の中で何を主張しているか? これはひとことでまとめると:
資本のリターンが生産や所得の成長率を超える場合、資本主義下では格差が拡大しやすい。それは19世紀にも見られた現象だが、いま、21世紀にも再現しようとしている。これがおきてしまうと能力や努力に報いる社会をむしばみ、民主主義の基盤を揺るがしかねないということだ。
以上、
ノーベル賞もらった連中が編み出した金融工学なんじゃらハゲタカ新自由主義経済(=紙切れ経済)が、現物資本主義を度過ぎて牛耳る世の中、破滅・整理淘汰されるまでには、まだかなり時間を要する。それまでは格差はますます広がるだろう。権力欲が銭だけに集中してしまっている世の中。マクルーハンが述べたとおり、銭持ち側がメディアを通して国民全体を洗脳し、不満の声は小さくなるばかりかかき消される。
米経済は第2のリーマン・ショックが必ず起きる。そこでは、米経済を立て直した奇跡のIT革命もシェールガス革命もすでに終わり、日本がそうであったように、また、欧州が長期間苦しんでいるように再起のきっかけはなかなか見出せないものになる。そこに、ハゲタカ経済が破壊され尽くし(修正不可能なリーマンハゲタカ経済の破滅)、修正されてくることに期待したい。


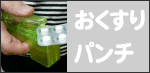








コメントをどうぞ