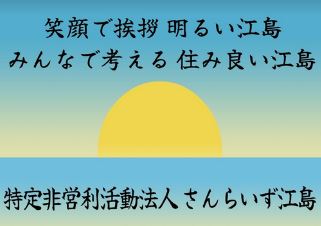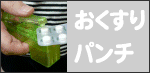"国を安売り"するインバウンド偏重政策の末路
"国を安売り"するインバウンド偏重政策の末路
円安と観光立国政策が交差する中、日本経済は危うい岐路に立たされている。安易なインバウンド依存と通貨安誘導が、国内産業と国民生活に深刻な副作用をもたらしているからだ。
近年、政府は「観光立国」「インバウンド消費」を成長戦略の柱とし、訪日外国人の数や消費額を喧伝してきた。円安の進行は、外国人旅行者にとって日本を「割安な旅行先」とする効果をもたらし、一部の観光地や百貨店は潤ったように見える。しかしそれは、通貨価値を意図的に下げてまで国を“安売り”して得た短期的な外貨収入に過ぎない。
このような構図は、国家としての本質的な経済力の弱さを露呈させる。「高品質なモノやサービスを、適正な価格で提供する」本来の経済戦略とは対極だ。労働力、土地、商品が「安いから売れる」国へと堕している現状は、国の威厳と経済主権を損なう危険な兆候だ。
円安によって得られるインバウンド収入の裏側では、輸入物価の高騰や実質賃金の低下といった“見えない重税”が国民を圧迫している。観光客で賑わう都市部の光景とは裏腹に、地方では生活コストの上昇が進み、購買力が奪われている。
本来、インバウンドは「副産物」であるべきで、国の経済を支える“主軸”ではない。観光消費を外貨獲得の切り札とするような戦略は、国内産業の再生や内需拡大という本筋から逸脱しており、結果として“外需依存体質”を助長するだけだ。
目先の観光収入を追い求めて国の経済基盤を空洞化させる――。そんな“安売りニッポン”の幻想は、そろそろ見直す時期に来ている。