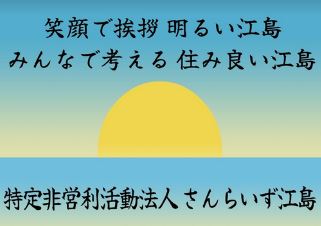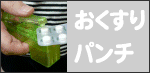農協改革、問われる"攻め"と"依存"の二重構造
農協改革、問われる"攻め"と"依存"の二重構造
米価高騰をきっかけに、またもや農協改革論が浮上している。「農協悪玉論」は事実に基づかない面もあるが、同時に農協自身の改革の遅れが現在の閉塞感を招いた側面も否定できない。
たとえば、日本のコメは品質の高さに定評がありながら、世界市場でブランド化しきれなかった。TPPやEPAといった貿易協定が進む中でも、農協が国際展開に本腰を入れてきたとは言い難い。国内市場が縮小する中で「守る農政」ばかりを追い、輸出による高付加価値化という“攻めの農政”に転じられなかったのは、大きな機会損失だった。
また、農林中央金庫が抱える約100兆円の預金は、主に全国の農協・JAバンクを通じて農家などから集められた資金である。この資金の背景には、長年にわたる農政の枠組み――たとえば減反政策や価格支持制度など――が存在してきた。農家は、政府の方針に沿って作付けや経営方針を調整しながら、必要に応じて農協経由で資金を借り入れ、事業を維持してきた。結果として、農協の信用事業は農業政策と密接に結びついた構造となり、その集積された資金が農林中金に集約されてきたという側面がある。
この構図は、農協と政府の間に長年にわたって続いた“共依存関係”の表れでもある。農業金融が、単なる民間の信用取引ではなく、政策の延長として機能してきた歴史を踏まえると、農林中金の資金もまた、一定程度は農政の帰結として蓄積されたと見るのが自然であろう。
農協の役割を全面否定するのは誤りだが、農業政策が特定の団体と制度に依存し続ける構造もまた、見直しが必要だ。農協改革の本質は、組織をつぶすことではなく、農家が主体的に未来を選べるような仕組みへと進化させることにある。守りと依存から、攻めと自立へ――。本当の意味での改革は、そこにこそある。